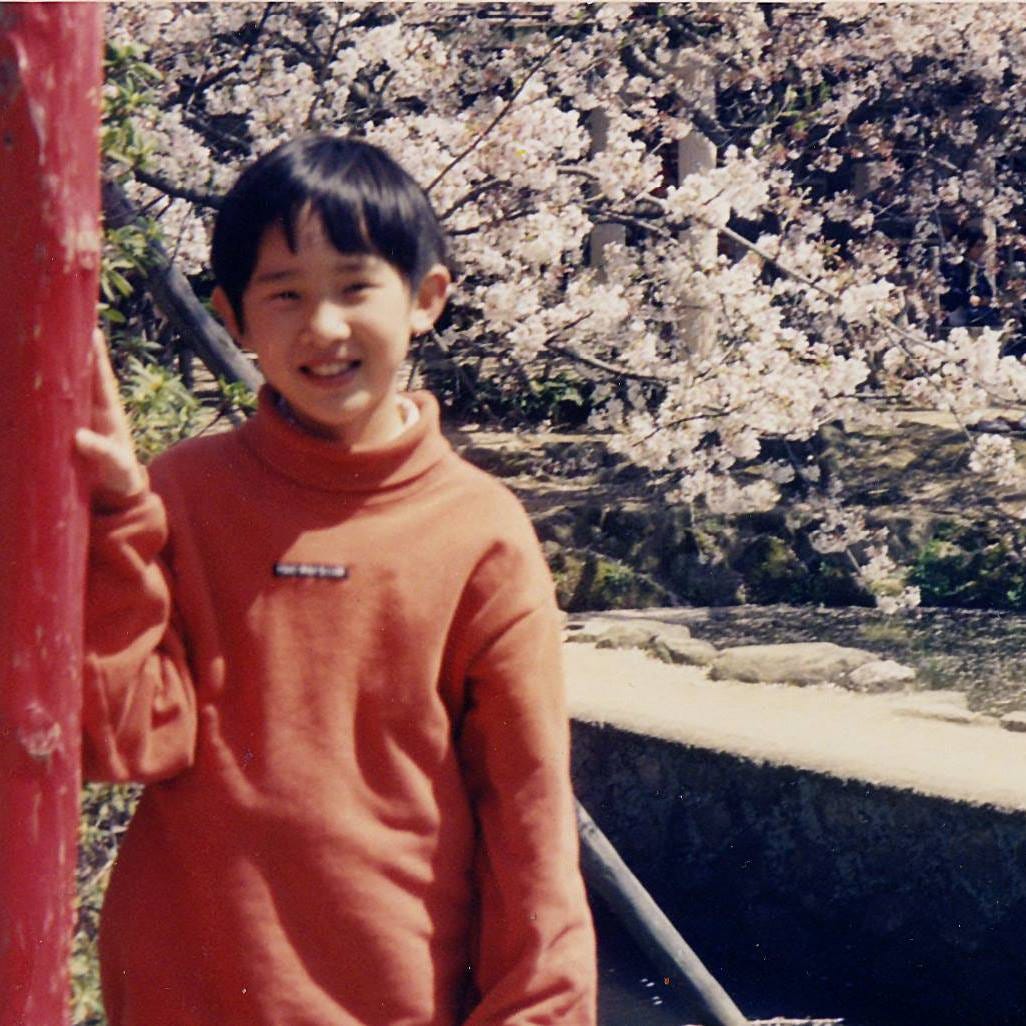わたしは高校生のとき、祖母と暮らしていた。祖母は、「おばあちゃん」と呼ばれるのがいやで、「大きなママで、大ママちゃんと呼びなさい」と言った。だからわたしたち三姉妹は「おままちゃん」と彼女を呼んだ。大好きだった。いっしょにいるだけで毎日が楽しかった。不機嫌になってかんしゃくを起こすところも、スーパーに出るだけなのに真っ赤な口紅をひくところも、食べることに執着しておいしい料理をつくることに並々ならぬ情熱を燃やすところも、大好きだった。祖母が自転車に乗ったことがないというので、彼女をうしろにのせてスーパーまで二人乗りした。あのときの重さは一生忘れないと思う。六十九歳ではじめて自転車にのったんだ。
おままちゃんはわたしが大学生になるのを待たずに亡くなった。だけどわたしはずっとおままちゃんと生きている。おままちゃんがずっと一緒にいてくれるような気がする。どこに行ってもずっと。
海外に住むのは孤独になりがちだけれど、わたしの場合、いろんなところで「おばあちゃん」に助けてもらう。おばあちゃんたちからかわいがられる。それがなぜなのかはわからないけど、わたしは勝手に、おままちゃんが話をつけてくれてるからだと思うことにしている。
トロントに住んでいたときは、ラトビア、ウクライナ、イタリア、香港からのおばあちゃんたちが、いっせいにわたしに食べ物を与えてくれるようになり、お話をしてくれるようになり、寂しい思いをしたことがない。いっしょにサイクリングに行ったり、コンサートに行ったり、料理教室をしたりする。なんちゃって、難民高齢者への英語教育ボランティアをしていたことが大きいと思う。週に1回、コミュニティセンターで教室を開いていた。なぜかポッドラックパーティーになった。いくみはおいしそうに食べるからと、どんどん食べものを持ってきてくれた。
今、エドモントンに住んでいるけど、ここでもおばあちゃんが助けてくれる。マイケルの看病と夏休み育児でへとへとなわたしは、4歳児の送り迎えに1万歩歩かねばらならない。なぜならわたしはここでは運転免許を持たず、送迎係だったマイケルは身動きが取れないからだ。すると、保育園までの中間地点に住むドイツ移民のリタおばあちゃんが、玄関先に水とおやつを用意してくれるようになった。ただそこに置いてあるときもあれば、出てきて話をするときもある。「ちょっと休んでいきなさい」とそう言ってくれるのが、とてもありがたい。その裏に住んでいる、カナダ人おばあちゃんルースは、4歳児にお花のレッスンをしてくれる。4歳児が花が大好きだ知ってから、「あんたは偉大な植物学者になるよ」と言って、花の名前や特性などを教えてくれる。花を両手いっぱいに持たせてくれる。家に帰ると上階に住むルーマニア人のおばあちゃん、モニカがクレープを持っておりてくる。クレープ生地にラズベリージャムをたっぷりぬって、くるくるってまいたやつだ。トロントで親しかったラトビア移民のヴァリアおばあちゃんのクレープとおんなじで泣きそうになる。わたしはクレープは巻かずに食べたい。わたしはラズベリージャムが苦手。だけど、おばあちゃんが大好きすぎて、笑顔でほおばる。完食する。ありがとう。ありがとう。と言う。きっと、このラズベリーくるくるクレープをまた出される。だけど、これは苦手ですと言う気にはなれない。チャーミングで押しが強くて、大好きな人たちだ。
そういう日常のひとときが、いかに心をほっとさせてくれるか、彼女たちは分かっている。わたしも分かっている。だけど余裕がないと、自分にそういう瞬間をゆるしてあげることができない。黙々と歯を食いしばってやり遂げようとする。だからそんなとき、ばーんっとおせっかいに、体当たりで、休憩させてくれる人たちの存在がすごくありがたい。
高校生のとき、毎日3時間英語の勉強をすると机にかじりついていたわたしに、おままちゃんが料理を手伝えと言ったように、この焼肉丼のソースにしょうゆをいれるべきか、バターをいれるべきか聞くためだけにわたしのヘッドフォンをひっつかんだように、こういう強引なやさしさが必要なときがある。
この見極めができる彼女たちを、わたしはまじで尊敬している。
ああいう大人になりたい。すげえかっこいい。